1.はじめに
転勤族としての暮らしは、常に新しい環境との出会いの連続です。大人にとっては「仕事の都合」や「キャリアアップのチャンス」と捉えられる転勤も、子どもにとっては生活環境が大きく変わる大事件。なかでも「転校」は、子どもの心に少なからずストレスや不安をもたらします。
実際に「転勤 子ども 不安」と検索する保護者の方が多いように、引越しによって子どもが感じるストレスや不安への対処に悩むご家庭は少なくありません。
友だちとの別れ、慣れ親しんだ先生とのお別れ、新しい学校や通学路、校則の違いなど、子どもにとっては変化の連続。こうした環境の変化に対して、戸惑いや緊張、時には拒否反応を示すこともあるでしょう。

だからこそ私たち親は、ただ「転勤だから仕方ないよね」と伝えるのではなく、子どもが転勤や転校を前向きに受け入れられるような声かけやサポートを意識していくことが大切です。
この記事では、これまでに5回の引越しを経験してきた我が家の実体験をもとに、
- 子どもが転勤を前向きに捉えるための声かけの工夫
- 転入先の学校をチェックする際に見ておきたいポイント
- 新しい環境にスムーズになじむための準備とアイデア
- 親自身のメンタルケアの大切さ
について、具体的にまとめていきます。


転勤が決まったんだけど、子どもにどう伝えたらいいか悩んでるの。急に新しい環境に慣れるのが不安だと思うんだけど…

その気持ち、よく分かります。でも、子どもは親の気持ちをよく感じ取りますから、ポジティブに伝えると安心しますよ。例えば、『新しい場所で楽しいことが待っているよ』って、期待感を持たせるといいですね。

でも、転校や引っ越しが怖いって思うかもしれないし、不安な気持ちもどう伝えたらいいか…

はい、その通りです!子どもも親が前向きだと安心するので、焦らず一緒に乗り越えようという気持ちを伝えてあげると、スムーズに心が落ち着きますよ。
2. 子どもの心に寄り添う|転勤・転校を前向きに捉えさせる声か

「転勤っていやだ!」その言葉には理由がある
引越しの話をしたとき、子どもが「転校したくない」「友だちと離れたくない」と言うのはごく自然な反応です。特に小学校中〜高学年以降は、友人関係や所属意識が強くなる時期。子どもにとって学校は、家と同じくらい大切な居場所です。
そんなときに「またすぐ新しい友だちができるよ!」などと軽く流してしまうと、子どもは「ちゃんと気持ちをわかってもらえていない」と感じてしまいます。
まずは不安や悲しみを受け止め、**「そうだよね、寂しいよね」**と共感することが第一歩です。
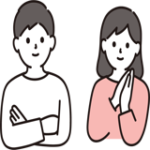
なるほど、共感しながら前向きな気持ちを伝えることが大事なんだね。

はい、その通りです!子どもも親が前向きだと安心するので、焦らず一緒に乗り越えようという気持ちを伝えてあげると、スムーズに心が落ち着きますよ。
年齢別|気持ちに寄り添う声かけのヒント
■ 幼児〜低学年(3歳〜小2くらい)
この時期の子どもは、「なぜ引っ越すのか」という理由よりも、「安心できる人(=親)が一緒かどうか」を重視します。説明は短く、でも前向きな印象になるように伝えましょう。
例:
- 「新しいおうちに行くよ。お父さんもお母さんも一緒だよ」
- 「新しい幼稚園にはすべり台があるかもね!見に行こうね」
- 「おもちゃも一緒に行くから大丈夫だよ」
「大好きなもの・人は一緒にいる」という安心感を伝えることが大切です。
■ 小学校中学年〜高学年(小3〜小6)
この時期の子どもは、友だちとのつながりをとても大切にしています。無理にポジティブ変換せず、「別れのつらさ」にしっかり寄り添ったうえで、少しずつ新生活の楽しみも伝えていきます。
例:
- 「〇〇ちゃんと離れるの、つらいね。ずっと仲良しだったもんね」
- 「お別れは悲しいけど、〇〇ちゃんには手紙を書こう。きっと喜んでくれるよ」
- 「新しい学校で一番に気になること、教えてくれる?」
子どもの「気持ちを話す力」を引き出すように、質問や共感を繰り返すのがコツです。
■ 中学生以上
反抗期と重なる時期でもあり、感情を表に出しにくくなることも。頭ごなしに励ますのではなく、「大人のひとり」として信頼し、自主性を尊重する姿勢がポイントです。
例:
- 「転校ってしんどいよね。私もそうだった」
- 「どんなサポートがあれば、少し楽になると思う?」
- 「つらいときは、無理に前向きにならなくてもいいよ。ゆっくりで大丈夫」
子どもが「この人は自分を理解しようとしてくれてる」と感じることで、安心と信頼が生まれます。
前向きな気持ちは「押しつける」ものではなく「育てる」もの
転勤に対して前向きな気持ちを育てるには、「転勤=新しい出会い」や「自分を成長させてくれる経験」と捉える思考を、親がまず持つことも大切です。
親がイライラしていたり、「また転勤か…」と愚痴をこぼしてばかりいると、子どもは敏感にその雰囲気を感じ取ります。逆に、親が新しい土地に楽しみを見つけていたり、新しいチャレンジを前向きに語っていると、それは子どもにとっての「心の土台」になります。
「知らない場所に行くのはちょっとドキドキするけど、新しい発見があるかもね!」
そんなふうに、ちょっとした言葉がけで、子どもの心は少しずつ未来に向かっていきます。

3. 子どもの不安を減らす準備行動
転勤や転校は、子どもにとって「未知への飛び込み」です。大人以上に見通しが立てづらいため、「知らない」「わからない」が不安に直結しやすいもの。
このパートでは、引越し前にできるちょっとした工夫で、子どもが新しい環境を受け入れやすくなる準備行動をご紹介します。
① 新しい土地や学校の情報を一緒に調べる
「知らない」が不安なら、「知る」ことで安心に変えていくのが基本です。引越し先の街や学校の写真、通学路、遊び場、ランドマークなど、Googleマップや市区町村の公式サイト、YouTubeなどを使って一緒に見てみましょう。
親子で一緒に調べることで、楽しさや安心感が生まれます。
話し方の例:
- 「この道を通って学校に行くんだって!桜並木がきれいだね」
- 「近くに大きな公園があるよ。すべり台、見てみる?」
- 「給食の献立、ちょっと違うみたい!楽しみだね」
子どもにとって「具体的にイメージできるかどうか」は安心材料としてとても重要です。
② 今の学校や友だちとの“お別れ”を大切にする
ついつい「次の学校にどうなじめるか」にばかり意識が向きがちですが、今いる場所との“しっかりとしたお別れ”ができると、心に区切りがついて、前に進みやすくなります。
「別れを悲しむことは、今の生活が幸せだった証拠」
そんな気持ちに寄り添いながら、次のステップに進めるようにしましょう。
実践例:
- お別れ会を開いてもらう(先生に相談して調整)
- アルバムや手紙交換で「ありがとう」を伝える
- 「転校ノート」や「寄せ書き」をもらう(自分からお願いしてもOK)
中には、最後の日に友だちと写真を撮ったり、おそろいの小物を買って思い出にするご家庭もありますよ。
③ 気持ちを言葉にする「親子の会話タイム」をつくる
引越しが近づくにつれて、子どもは言葉にできない不安を抱えやすくなります。大人の目には見えないけれど、眠りが浅くなったり、イライラしたり、甘えが強くなったりと、さまざまな形で表れます。
そんなときこそ、1日5〜10分でも「子どもの気持ちを言葉にする時間」を持つように心がけましょう。
会話のヒント:
- 「今日、学校で一番楽しかったことってなに?」
- 「今、不安なことがあったら教えてね。どんなことでもいいよ」
- 「引越しまでにやっておきたいこと、一緒に考えようか」
**「ちゃんと話を聞いてくれる大人がいる」**という安心感は、子どもにとって何よりの支えになります。
④ お気に入りのアイテムを一緒に「お引越し準備」
子どもの心を落ち着かせる“安心アイテム”を一緒に荷造りすることで、気持ちの準備にもつながります。ぬいぐるみ、絵本、筆箱、手紙、写真……どんなものでもOKです。
「これは新しい家でも持っていくね」「一緒にお引越しだね」と声をかけてあげましょう。
4. 転入先の学校チェックリスト

転校先の学校がどんな場所か、事前に情報を集めておくことは、子どもの不安を減らすためにも非常に大切です。新しい学校の雰囲気や通学路などを知ることで、子どもがスムーズに慣れる手助けになります。
ここでは、転校前にチェックしておくべき重要なポイントをご紹介します。学校選びや入学後の不安を最小限にするために、ぜひ参考にしてください。
① 学校の雰囲気を感じ取る
まず、学校全体の雰囲気を感じ取ることが重要です。学校によって、学年ごとの特色や教育方針、先生の教え方などが大きく異なることがあります。
確認すべきポイント:
- 学校のHPやSNSがあれば、情報をチェック。学校行事や活動の様子を知ることができる
- 学校の規模(クラスの人数、学校の広さ)や施設(運動場、図書室、保健室など)の確認
- 学校見学やオープンスクールがあれば参加して、実際に学校の雰囲気を肌で感じる
子どもが実際に学校で過ごす時間は長いので、「自分がここで過ごすイメージ」を持たせることが大切です。
② 通学路や周辺の安全性
転校先が決まったら、通学路の安全性を確認することも重要です。通学路に危険な場所や不安なポイントがないか、事前にチェックしておきましょう。
確認すべきポイント:
- 通学路に交通量が多い場所や危険な交差点がないか
- 登校班がある場合、参加方法や集合場所を確認
- 近隣の治安や子どもが遊ぶ場所の安全性(公園や遊具など)
通学路や登校班の情報を事前に調べておくことで、毎日の通学が安心して行えるようになります。
③ 学校のルールやカリキュラム
転校先の学校のルールやカリキュラムも、子どもにとって大切な情報です。特に、学校独自のルールや文化がある場合、早めに理解しておくことで戸惑いを減らすことができます。
確認すべきポイント:
- 学校の校則や服装規定(制服の有無、持ち物、髪型など)
- 学年ごとの授業内容や進度、使用する教科書
- 学級ごとのカリキュラムや特別支援が必要な場合、そのサポート体制
学校のルールに関する情報は、転校面談や学校見学の際に先生に確認したり、学校案内の資料に記載されていることが多いので、しっかりチェックしておきましょう。
5. 新天地での生活スタートをスムーズにする工夫

転勤後の新しい生活は、最初はどうしても不安がつきものです。特に子どもは、知らない場所や環境に対して強い抵抗感を持つこともあります。親としてできるだけ早く不安を取り除き、安心して新しい生活をスタートできるような工夫を取り入れることが大切です。
このパートでは、転勤後に実践すべき「新生活スタートの工夫」を具体的に紹介します。子どもが新しい環境に早く馴染むために、どんなサポートが必要なのかを考えていきましょう。
① 「新しい生活」のルーチンを作る
転勤後、子どもが安心できる一番の方法は、生活のリズムを安定させることです。学校生活や家庭生活で、なるべく同じ時間に同じことをすることで、子どもは安心感を覚えます。
実践のヒント:
- 朝の準備や就寝時間をできるだけ一貫性を持たせる
- 食事の時間を決めて、家族全員で一緒に過ごす時間を大切にする
- 週に1〜2回、家族で近くの公園や遊び場に出かけることを日課にする
安定した日々を送ることで、子どもは「新しい場所でも自分の居場所がある」と実感しやすくなります。
② 新しい学校での「初日」をサポートする
新しい学校での初日は、どうしても不安が大きいものです。学校に通い始めたばかりのころは、特に緊張している子どもが多いので、親としてできるだけサポートしてあげましょう。
実践のヒント:
- 初日の服装や持ち物を事前に確認して、余裕を持たせる
- 「今日はどんなことがあった?」と帰宅後すぐに声をかけ、ポジティブな部分を引き出す
- 初日は、無理に学校行事に参加させるのではなく、少しずつ学校生活に溶け込ませる
学校に慣れるまでは、無理に「楽しんでね!」と強調するのではなく、「落ち着いてやれば大丈夫」と励ます言葉をかけることが効果的です。
③ 新しい友だちを作る手助けをする
新しい学校での友だち作りは、子どもにとって大きなチャレンジです。学校の初日から友だちができるわけではないため、少しずつ子どもが自分から友だちを作れるようサポートすることが大切です。

実践のヒント:
- 「学校の友だちができるといいね」と言いつつ、あまり焦らせないようにする
- クラスの活動に積極的に参加するように促す(クラブ活動やグループ学習など)
- 家族で地域のイベントやコミュニティに参加して、学校外の友だちを作るチャンスを増やす
子どもは無理に友だちを作ろうとするとさらにプレッシャーを感じることがあります。「焦らずに」少しずつ慣れていけるように手助けしてあげることが大切です。
④ 子どものストレスに気づくサインを見逃さない
転勤後は、子どもの心が疲れやすくなることもあります。環境の変化に対するストレスを見逃さないように、日常的に子どもの様子をチェックしましょう。
ストレスのサイン:
- 睡眠の質が落ちる(夜中に目が覚める、寝つきが悪い)
- 食欲が落ちる
- 突然の感情的な反応(イライラや涙)
もしこのようなサインが見られた場合、無理に「がんばれ」と励ますのではなく、気持ちを聞いてあげることが重要です。子どもの話をしっかり聞いてあげることで、不安が軽減されます。
⑤ 親のメンタルケアを忘れない
親が元気でないと、子どもにもその影響が出てしまいます。転勤という大きな変化は、親にとってもストレスが多いもの。自分のメンタルケアをしっかり行うことが、子どもにとっても良い影響を与えることを忘れないようにしましょう。
実践のヒント:
- 定期的にリラックスする時間を作る(趣味や友達と話す時間、静かな読書など)
- 転勤後の新しい地域で支え合える友人を作る
- 必要に応じて、地域のサポートサービス(カウンセリングやサポートグループなど)を活用する
親が前向きでいると、子どもも自然とその姿を見習います。親のリラックスした姿勢が、子どもに安心感を与えることになります。

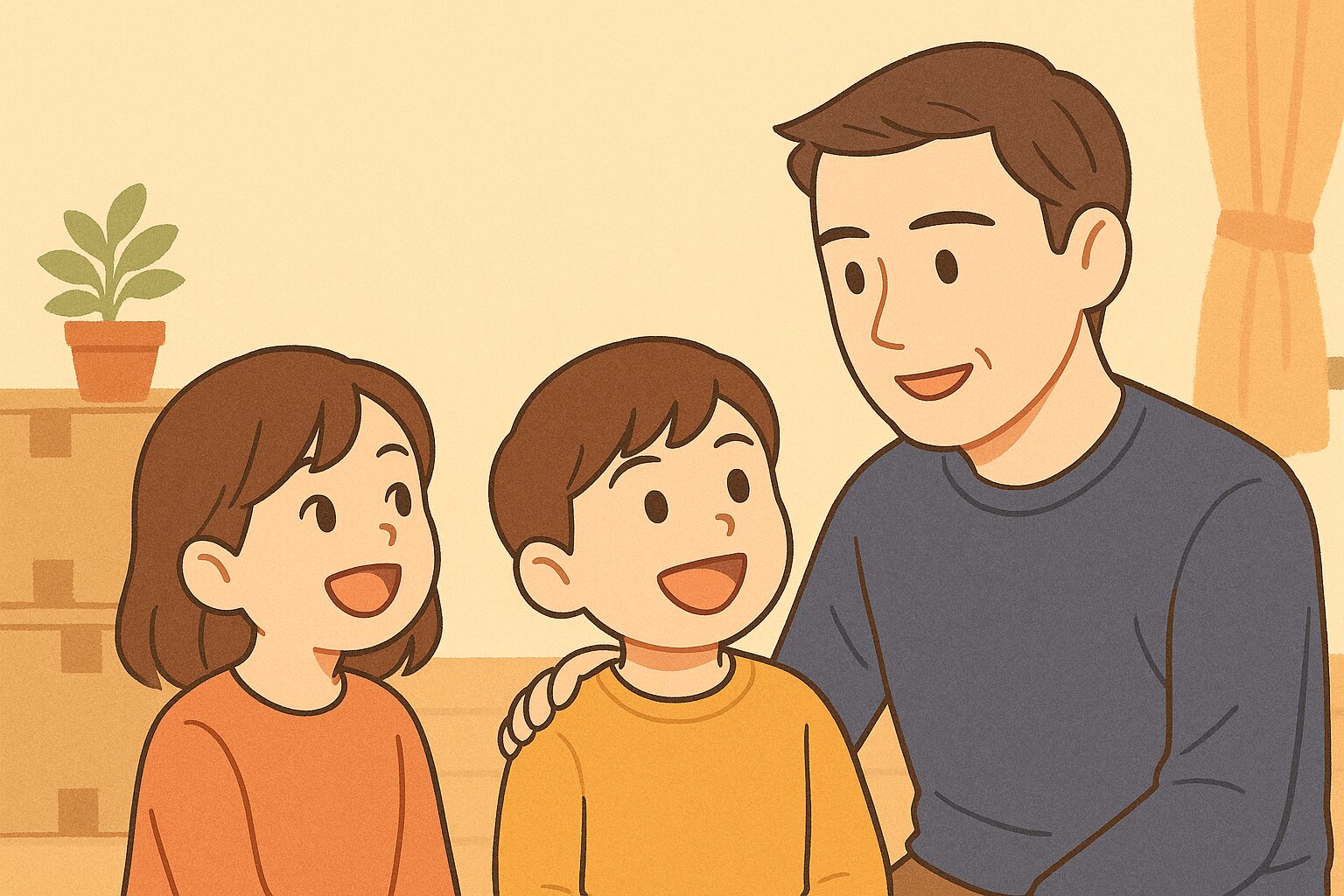


コメント